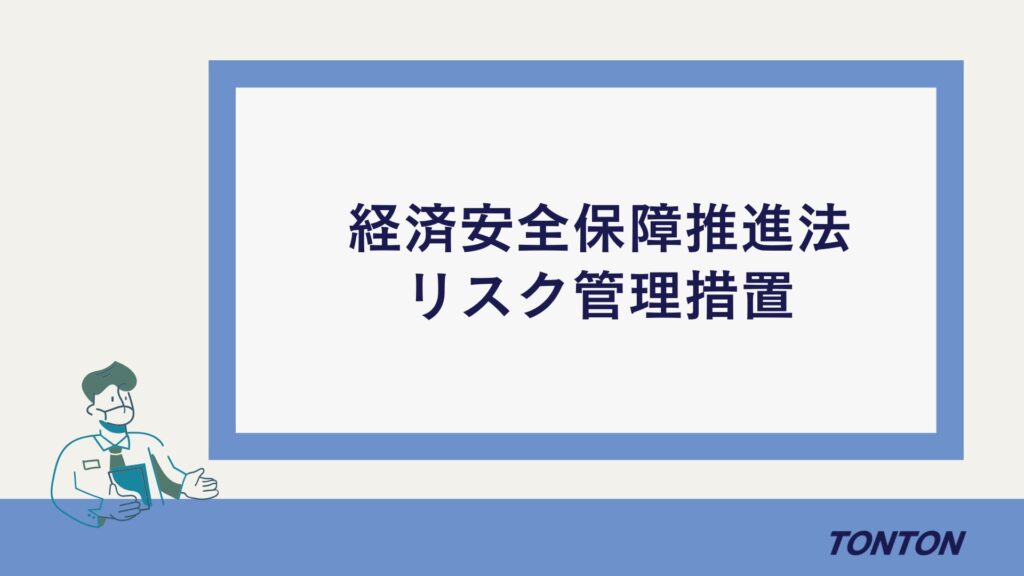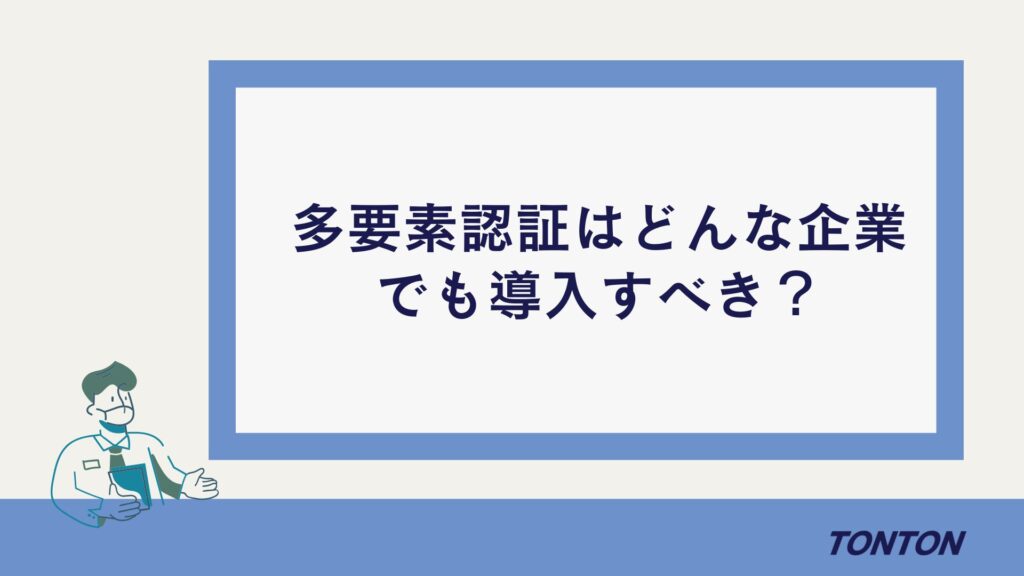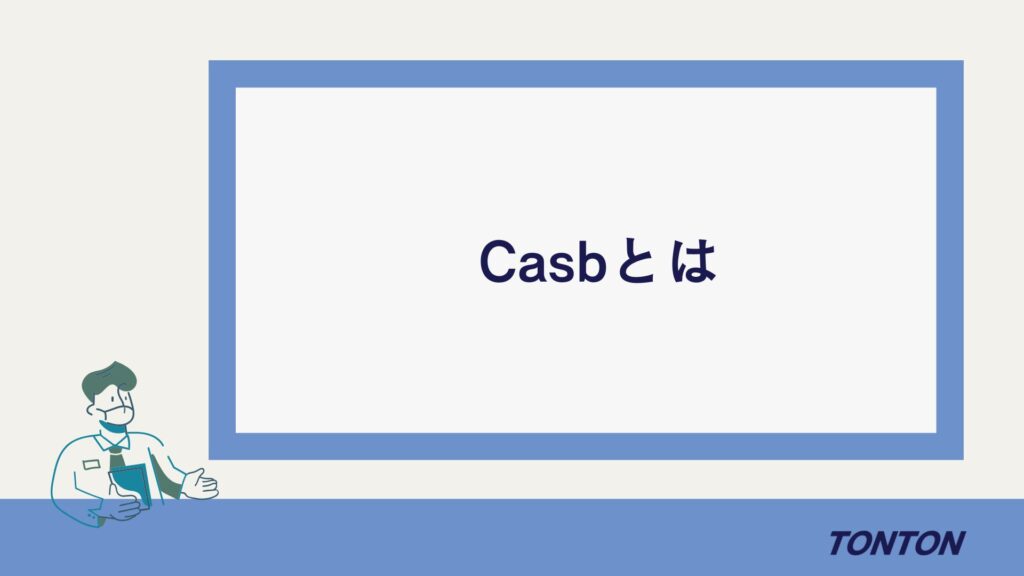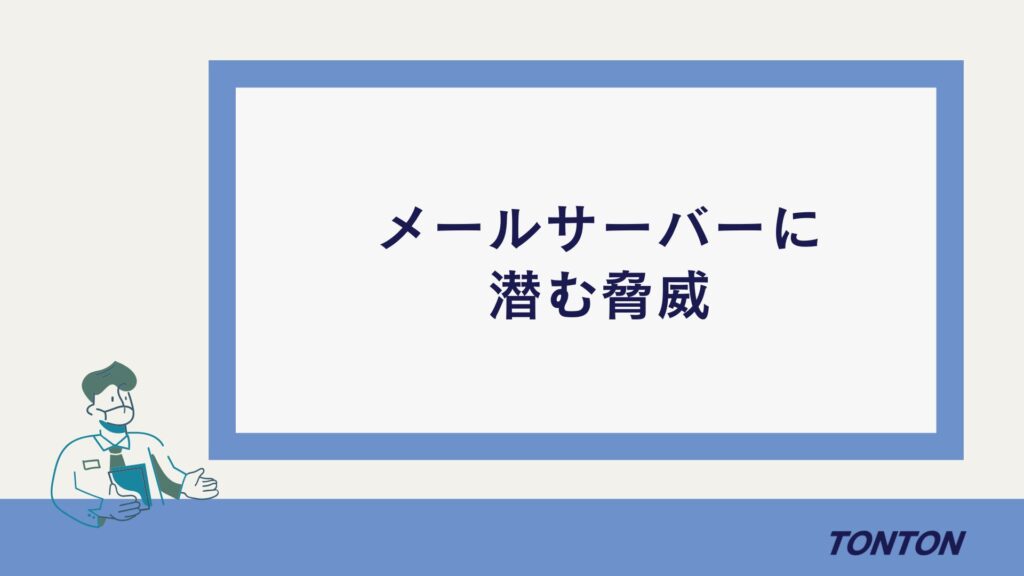2025.03.28
脆弱性診断はなぜ必要?種類やツールの選び方のポイントを解説
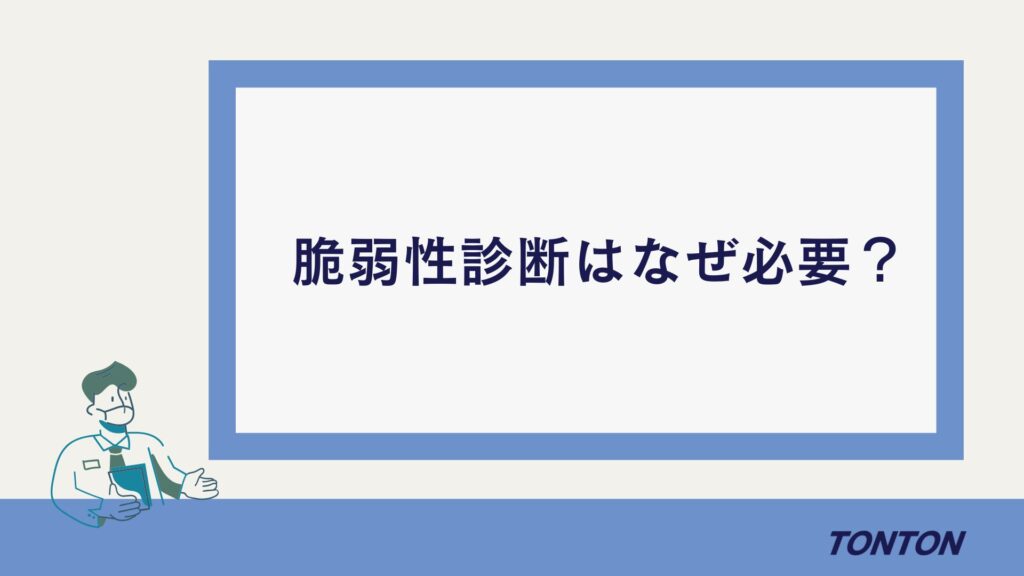
日本国内では、サイバー攻撃による被害が増加しており、多くの企業が影響を受けています。ビジネスのデジタル化を進める企業が増える中、AIや自動化ツールを活用した、サイバー攻撃も増加傾向です。AIや自動化ツールを活用して、従来よりも短時間で、広範囲な攻撃を仕掛けるケースも増えています。
サイバー攻撃に対応するためには、脆弱性診断が有効です。脆弱性診断を実施することで、悪用される前にシステムの脆弱性を発見し、適切な対策を講じて、企業の大切な情報資産の保護が可能です。診断結果をもとに適切なセキュリティ対策を実施することで、システム全体の安全性を向上させられます。
この記事では、脆弱性診断の必要性や種類、ツールの選び方のポイントなどについて解説していきます。
脆弱性診断の必要性
脆弱性診断は、WebサイトやWebアプリケーション、ITシステム、ネットワークなどに潜むセキュリティ上の脆弱性を発見しリスクを未然に防ぐための取り組みです。サイバー攻撃の手法は年々高度化、複雑化しており、企業の情報資産を狙った攻撃が増加しています。
セキュリティリスクを抱えたままですと、情報漏えいやシステム改ざんなど深刻な被害に繋がりかねません。脆弱性診断を実施することで、悪用される前に脆弱性を発見し修正できます。診断結果は共通脆弱性評価システム(CVSS)などの国際的な指標に基づいて危険度が評価される仕組みです。優先順位をつけて効率的に、対策を進められる点も重要です。
脆弱性診断の種類
脆弱性診断の種類は、主に「ツール診断」・「手動診断」に分けられます。ツールを使った自動スキャン、手動で行う詳細な診断のどちらが適しているのかは、ケースバイケースです。自社の予算やニーズに合わせて、最適な脆弱性診断方法を取り入れましょう。
ツール診断
自動化による脆弱性診断がツール診断です。脆弱性診断の実施から結果まで自動化されており、最短5分間位で完了する診断ツールもあります。インターネットを介して、Webブラウザから手軽に使用でき、効率的に広範囲の診断が可能です。ツールによって対応可能な診断範囲や精度は異なります。高精度なツールほど誤検知率が低くなるため、診断結果の分析時の負担軽減につながるでしょう。
手動診断
手動診断はサイバーセキュリティに関する専門知識を持つ人物が、システムやアプリケーションを、自らの手で診断する方法です。専門技術者のスキルや知識によって、診断精度の質が変わるのが特徴です。経験豊富な専門技術者の場合、機械的には見つけにくい脆弱性も発見につながる可能性が高いでしょう。自動化ツールだけでは対応できない部分があれば、手動診断との併用も検討すべきです。
ツールの選び方のポイント
ここまでで、脆弱性診断の必要性や種類についてお伝えしてきました。企業の情報資産の安全性を高めるためには、脆弱性やセキュリティ脅威の早期発見が大切です。診断ツールの導入を検討する場合、いくつかの押さえておくべきポイントがあります。
次の項目では、脆弱性診断ツールの選び方のポイントをお伝えしていきます。
- 診断範囲と精度
- 費用対効果と予算に合わせた選定
- サポート体制や実績の確認
- 自社ニーズに合った導入方法
1.診断範囲と精度
脆弱性診断ツールを選ぶ際には、診断範囲と精度が重要です。ツールによって対応可能な診断範囲や精度は異なるため、システム全体で、どこまでカバーしたいか明確化する必要があります。
例えば、ツール診断では専用ソフトウェアを用いて自動的に検査を行いますが、一部の項目では手動診断が必要になる場合があります。手動診断は専門技術者による詳細な調査が可能です。一部ツールは特定のものしか対応していないため、自動化ツールだけでは対応できない部分について、手動診断との併用も検討すべきです。
2.費用対効果と予算に合わせた選定
ツールやサービスには、無料版から高額なものまで幅広く存在します。無料ツールと有料ツールでは、機能やサポート体制に違いがあるため、自社の予算や費用対効果を考慮した選定が重要です。無料ツールは初期コストを抑えられる反面、高度な機能やサポート体制には限界があります。
有料ツールは高精度かつ豊富な機能を提供しますが、その分費用も高額になります。セキュリティリスクへの予防やセキュリティ対策の実施は、一時的ではなく継続的に行わなければいけません。ランニングコストがかかってくるので、予算を圧迫しないように注意しましょう。
3.サポート体制や実績の確認
脆弱性診断ツールを導入する場合には、充実したサポート体制があるかどうかも重要です。初めて脆弱性診断を実施する場合には、技術的な支援が充実しているサービスを選ぶことで、安心して運用できるでしょう。過去の実績やユーザー評価も参考になります。
過去にどのような業種、規模の企業への導入実績の有無を確認することで、自社との相性を判断できます。同業他社で導入実績があるツールは、自社でも効果的に活用できる可能性が高いです。導入後トラブル発生時にも迅速かつ丁寧な対応が、期待できるかどうかも重要なポイントです。
4.自社ニーズに合った導入方法
企業によってオンプレミス型や、クラウド型など自社システム環境、運用体制などは違いがあります。自社システム環境や運用体制によって、脆弱性診断の最適な導入方法は異なります。脆弱性診断の効果を最大限に引き出すためには、自社ニーズに合った導入が大切です。例えば、オンプレミス環境ならソフトウェア型ツール、クラウド環境ならクラウド型サービスの導入が適しています。また、自社内で運用可能か、外部委託すべきかについても検討しましょう。
まとめ
脆弱性を放置することで発生する損害は、情報漏えいや企業の社会的信用の失墜など、企業存続にかかわる重大なものです。脆弱性診断は、企業の情報資産を守るための、セキュリティ強化において重要な取り組みです。サイバー攻撃から情報資産を守るためには、予防がとても重要になります。脆弱性診断の目的は単なる問題発見だけではなく、優先順位付けによる効率的な対策実施に繋がります。
自社ニーズに合ったツール選定や、適切な実施手順によって、効果はさらに高まります。定期的に脆弱性診断を実施して、自社システムの安全性を確保し、サイバー攻撃から情報資産を守りましょう。
閲覧ランキング
まだ集計されていません。